子どもは元気いっぱいに遊んでいることがほとんどですよね。
寒くなってきているけど、外でも走り回っています。
よく話を聞くのですが…
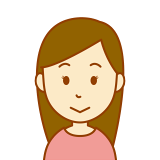
うちの子、落ち着いてレストランで座ってられないの…
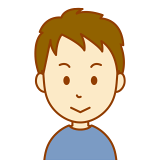
買い物に行った時も、言うこと聞かなくて、追いかけっこだよ…
こういった具体的な悩みを聞くことがあります。
では、実際に落ち着きがないという点について、どのように考えればいいのか?
家庭で実践できるような工夫や子どもへの指導などはないかな?
あれば、きっと実践してみたくなりますよね。
- 「落ち着きがない」ってどういうこと?
- 落ち着きがない原因って何があるの?
- 年齢によって問題視されることってどんな内容がある?
- 家庭で出来る指導や工夫できることってなにかない?
本記事では、上記の内容について記載していきます。
落ち着かずに困っていうという方々は読んでみてくださいね。
落ち着きがないとは?
落ち着きのなさ=ADHDという言葉を聞いたことはありませんか?
【ADHD:attention deficit/hyperactivity disorder】
≪昔の考え方≫
・極端に動く・不注意・衝動的なこどもを全般にいう。
・「微小脳損傷症候群」「微小脳機能不全」「小児期多動反応」「過活動児童症候群」など
≪今の考え方≫
・注意を集中or持続することが難しいから、多動や衝動的になる。
・「注意欠陥/多動性障害」と総称しています。

落ち着きがない子供とは?
基本的に、「子どもは落ち着きがない」と考えていてよいかと思います。
ただ、大事なのは?
簡潔にいえば、「時と場合でオン-オフが出来ているか?」になるでしょう。
(例)公共の場で静かにできているけど、家でははちゃめちゃ。
この場合はいいと思います。
家では迷惑をかけてもいいんだ!とわきまえているからです。
(例)保育園ので発表会の練習中、一人で歩いてどこかに行ってしまう。
この場合は、集団行動で協調性がなく、動いてしまっている。
こんな時は、環境調整などの配慮が必要なパターンです。

落ち着きがない原因とは?
1つとしては、遺伝的な要因が挙げられています。
具体的には、脳の前頭葉機能(前頭前野という前方の脳)の低下が考えられています。
ここは、感覚(例えば、目・耳・触覚など)と運動を制御する働きを担っています。
脳の神経伝達物質の、ドパミンやノルアドレナリンなどの働きが十分ではない。
このため、連携がうまくいかず不注意や多動の症状が出やすいと考えられています。

年齢ごとに表れやすい症状
目安として、年齢別で困ることや目立つ症状などを取り上げてみようと思います。
【乳児期:0~1歳】
基本的に手がかからない。
初語が遅い。
【幼児期前期:2~3歳】
多動、注意や集中が困難。
言葉の遅れがある。
人との関わりが希薄など。
【幼児期後期:4~5歳】
多動性、衝動性、不注意。
「集団生活の不適応」など。
【学童期(低学年)】
多動、不注意からの学習障害など。
【学童期(高学年)】
低学年症状+いじめ、乱暴、不登校など。
落ち着きのなさと言語の遅れなどは併発しやすいです。
特に1歳半健診などで、指摘を受けてだんだんとわかることが多いのが現状かと思います。

家庭でできる指導と工夫について
それぞれ個々に症状の特性があるため、一概には何とも言えません。
今まで指導の中で行ってきた方法の一部を記載していきます。

就寝前の絵本の読みきかせ
絵本の読み聞かせは、ぜひとも習慣化して行って欲しいです。
何分でも良いので、少しずつ。
言語獲得・発達にも良い効果があります。
得意なことを継続して苦手な分野を少し頑張る
お子さんが得意なことをメインで行ってもらう。
少し頑張ればできそうな苦手分野も間に挟んで行っていくことも大切。
最近接発達領域といい、ちょっと頑張ればできるところをトライさせることが一番発達を伸ばせるといわれています。
目につきやすい物やTVなどの刺激を少なくする
学習する場で、静かな環境を整えることが一番。
気になることがあれば、集中が途切れやすいのは、大人でもそうですよね?
集中させたい状況であれば、まずは環境を整えてあげましょう。

予定などを視覚的に提示する
聞いて理解するよりも手助けになることが多いです。
絵や写真でも良いと思います。
良く使うものは写真にしておくこと。
それをカードケースなどに入れておく。
裏に磁石を貼って、A4程度のホワイトボードなどに時系列で掲示できるようにしておくと、なお便利かと思います。
イメージは小学校の時間割を絵や写真にするような感じです。
これは臨床の場でも構造化といって、視覚的に手掛かりとするために用いることが多いです。

正の強化子を与えること
昔からいわれているのは?
「アメとムチ」という言葉ではないでしょうか?
子どもって、基本的にはアメだけでいいんです。
成功体験を積み重ねていくことで、自信につながり、頑張ろうとやる気をUPしていくものです。
ついつい、怒ってしまいがちですが、そこをこらえて指導していくことが大事です。
出来たら「褒める」、「達成シール」などをシールブックに貼るなど。
※正の強化子=その行動が増加・維持されるように働きかけることを指します。

安心する物や空間などの環境を整える
集中させたい場合は、やはり静かな環境のほうが、雑多な状態よりもいいとされます。
受験勉強や学習を効果的にしたい場合なども、静かな環境や、気がそれる物は近くに置かないなどと言われますよね。
小さい子供でも同じです。
興奮して攻撃的な場合など、本人が落ち着ける場所を確保しておくことも大事かと思います。
部屋の角に段ボールハウスやボールハウスなどを設置しておくことも大事。
衝動的で、動き回ってどこかに行く子どもなどは、効果的でした。
外出先などでは、本人が好きなおもちゃやタオルなどを持たせるようにする。
頭からかぶることで対応できたこともあります。

落ち着けるようにする治療方法
治療には「教育/療育支援」「薬物療法」の2つがあります。
これらは、自分自身の障害特性を理解し、行動をコントロールできるようになり、充実した生活が過ごせるようになることが最大の目的になるのではないかと思います。
教育と療育的支援
- 周囲の環境を整える
- 保護者が個々に合った具体的な対処法を学ぶ(ペアレントトレーニング)
- 本人が適切な行動を学ぶ(ソーシャルスキル・トレーニング)
これらが、基本的なものです。
子どもと親も含めて、言語聴覚士などの専門的な指導ができる職種から学んでいくようになります。
薬物療法
専門医を受診して判断してもらう。
診断名をつけてもらえないと、基本的には行いません。
必要に応じてですが、脳内物資のノルアドナリンやドパミンの不足を改善する働きのあるお薬を処方してもらうことが多くなります。

落ち着きがない子供への対応のまとめ
- 集中力を高める基礎トレーニングは読み聞かせ。
- 目につきやすい刺激は排除する。
- 視覚的にスケジュールを提示する(構造化)。
- 褒めて伸ばす(正の強化子)ようにする。
- 落ち着ける環境や物を考えてみる。
不安で困っている場合は、小児科医や言語聴覚士のいる病院などを探してみましょう。
または地域の健康福祉課や子育て課などの行政機関などに相談してみると良いかと思います。
抱え込まずに、相談することで楽になります。
お子さんに合った具体的な対応方法を検討してくれると思いますので、専門家を頼ってみて下さいね。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。少しでも解決につながることが出来れば幸いです。





コメント