前回は読み聞かせのねらいについて記載しました。
今回は、「絵本の読み聞かせ」を行うことで、どのような効果が得られるのかについて記載します。
子育てや育児の中では、読み聞かせを行う場面も数多くあると思います。
実際に大学院時代に使用した参考文献や調べた論文なども引用しながら解説していきたいと思います。
ぜひ、ご夫婦で読んでもらいたいです。
▶キャンペーン中で1300円無料
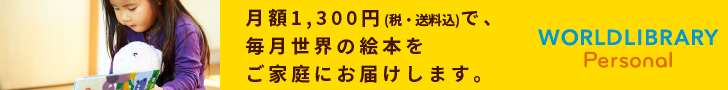
絵本の読み聞かせの効果とは?
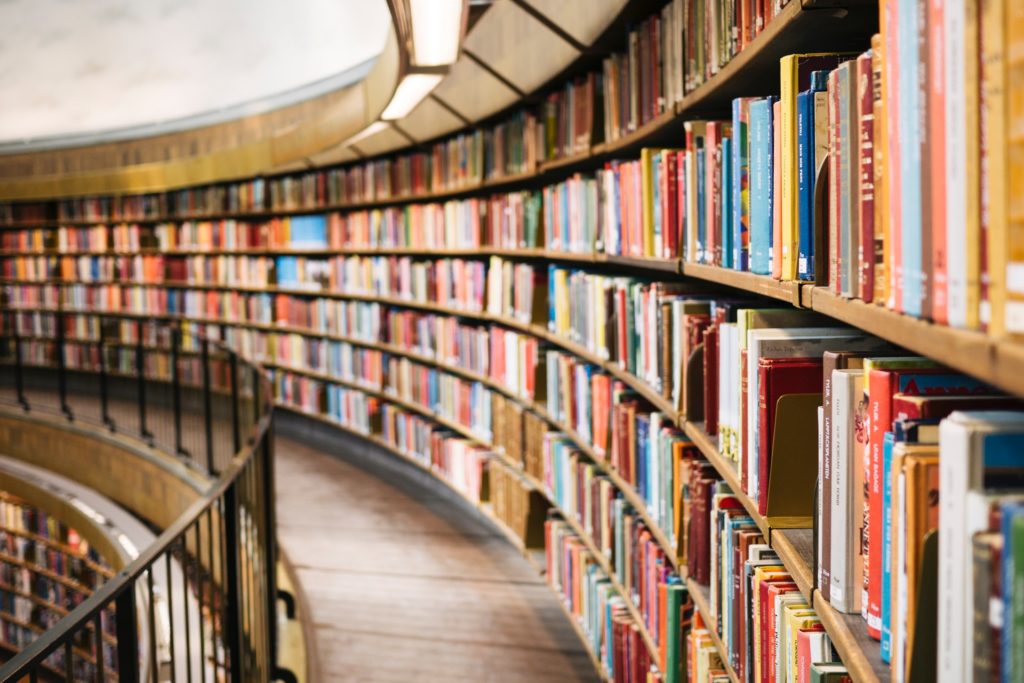
絵本の読み聞かせの効果はたくさんあります。
実際に確認してみましょう。
- 親子のスキンシップ
- 集中力が高まる
- 感情を豊かにする
- 言語表現やリテラシーを育む
- 認知能力の促進を図る
親子のスキンシップが図れる
「絵本の読み聞かせ」の効果として、まずは親子のスキンシップがより図れる時間が作れます。
一対一でお子さんと向き合って読んであげることで、読むことだけではなく親子との時間を共有しながら安心感なども育むことができます。
集中力が高まる
「絵本の読み聞かせ」を行うことで、集中力が養えます。
子どもは「どんな話だろう?」「どんな展開だろう?」「なんのことかな?」などと、言葉は分からなくても、絵などを視覚的に捉えて見ることで集中力が高まります。
感情を豊かにする
「絵本の読み聞かせ」を行うことで、子どもの感情が豊かになります。
文字だけではなく、絵などの展開から沢山の物語に触れることで、その子の感情を豊かにすることができます。
喜怒哀楽なども、絵から感じ取ることもできますので、たくさんの絵本を読んであげましょう。
言語表現やリテラシーを育む
「絵本の読み聞かせ」を行うことで、言語表現(言葉の表現力)や、リテラシー(気づくことの力)を養えます。
耳と目から入ってくる情報から、より言葉の表現力が見につきやすいです。
また、読んであげることで、「次の展開はどうなるんだろう?」「ここにリンゴが書いてる!!」などと、言葉を聞きながら分かったり、絵を見て気づいたりする力を高めることができます。
TVでも嫌な表現をマネしてしまったり、CMの言葉をマネしてしまったりは、こういった点からも学習を促進して言語表現の力が高まるんです。
認知能力の促進を図る
「絵本の読み聞かせ」を行うことで、認知能力の促進が図れます。
認知能力と言っても、先述した気づく力や言語能力も含まれます。
色々な考える力が身につくので、一概に語彙力だけを促進する物ではなく、総合的にいい刺激になることと考えてくださいね。
絵本の読み聞かせの効果は内生的・外生的な分類で考えられる
読み聞かせを行うことで、内生的意義・外生的意義の分類があるといわれています。
参考文献:秋田喜代美, 無藤隆.(1996)幼児への読み聞かせに対する母親の考えと読書環境に関する行動の検討.教育心理学研究1996;44 , 109-120
- 内生的な考え方
- 外生的な考え方
内生的な考え方
本を読むこと、その世界を楽しむことや内容を理解することそのものから生じる意義のことです。
読み聞かせにおいては本の世界を通じた親子の触れ合いを指します。
外生的な考え方
本を読むことの結果としての所産や効用が、他の目標の手段としてはたらくという意義のことです。
読解力や語彙力をつけるなどの認知的所産を期待するものを指します。
今回は、認知能力の促進という観点から、就学以降にもどう関わっていくのかについて、検討していきたいと思います。
絵本の読み聞かせの効果は認知能力の促進に大きく関与する
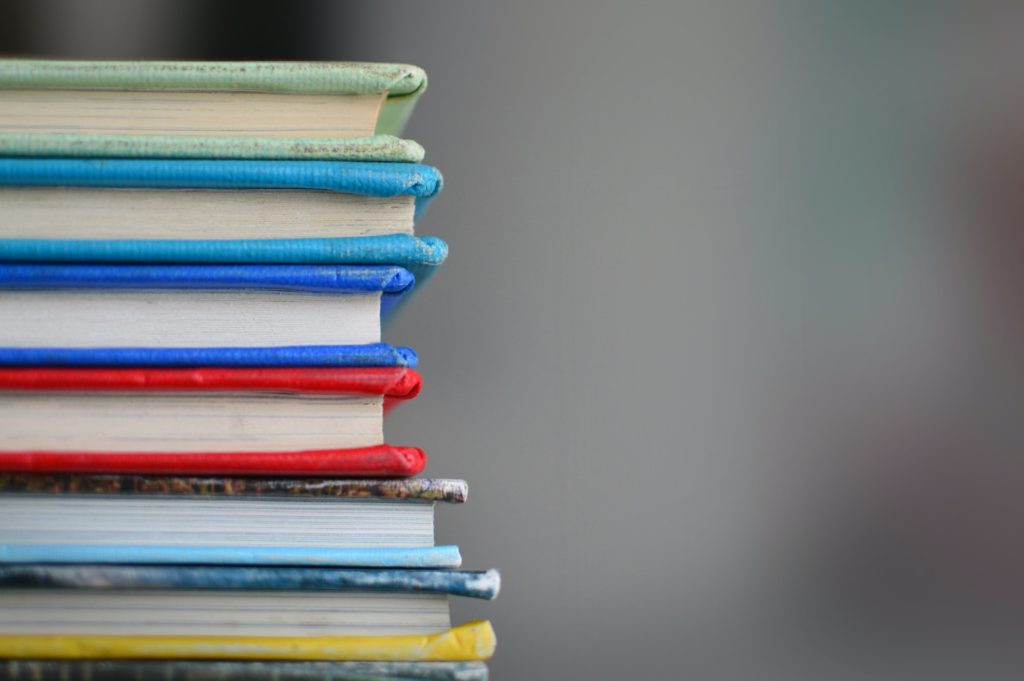
- 認知能力の中のワーキングメモリーに関与する
- ワーキングメモリーと知能との関連
認知能力の中のワーキングメモリーに関与する
「絵本の読み聞かせ」がもたらす、外生的な意義は先述した内容のように、文献内でも古くから定義されています。
ここで重要なのが、認知能力のなかに「ワーキングメモリ」(以下WM)という能力があります。
これは、アラン・バドリーという人が定義しています。
情報の保持に集中する短期記憶の概念を発展させ、読解・推論・学習などの高次認知的活動をするうえで必要な、情報の保持と処理・操作を同時並列的におこなう機能。
ワーキングメモリーと知能との関連
ワーキングメモリーはIQ(知能指数)との関連が高く示されており、WMが高いとIQも有意に相関するといわれています。
つまりは、WM=学業成績への影響があるといわれています。
4歳以降で読み聞かせが減りやすい状態ともいわれています。
ですので、しっかりと読み聞かせをしながら、WMなどの認知能力を高めることが出来るように、習慣化して実践していくことが大事です。
幼児期の読み聞かせが学業成績に影響を与える可能性があるという点について、認識しておきましょうね。
ワーキングメモリと学業成績との関連
参考文献:雨越康子、森下正修.幼児期の集団および家庭における絵本の読み聞かせと認知能力.日本教育工学会論文誌 2020;43(4),339-350
研究の一つで、上記の論文では、長期的な読み聞かせを行い、語彙力だけではなくWMが向上すかどうかについて、検討しています。
結論としては、語彙力は、既存の語彙をベースとして、未獲得な語彙の獲得が促進される。
WMは、記銘や想起を繰り返し継続することで能力が向上する可能性はあると思われる。
という結果になっています。
ですので、幼児期からの読み聞かせは、学業への関連性も十分に考えられ、早い時期から読んであげることが重要とされています。
【絵本の読み聞かせ】効果ってなに?子どもの語彙力と学業との関連の総括
- 幼児期からの読み聞かせが大事
- 語彙力だけではなく、総合的に認知能力を高める
- 認知能力の中でワーキングメモリーが重要
- ワーキングメモリーは学業成績との関連性が高い
- 早い段階からの読み聞かせを取り入れることが促進になる
以上になります。
少し専門的な内容にもなりましたが、読み聞かせは単に語彙力やスキンシップだけにとどまらないで、それ以降の学習を伸ばす要因になるという点について、分かっていただけたら幸いです。
なるべく早い段階で、お子さんに絵本の読み聞かせをたくさん行っていくと良いと思います。
何度も記載していますが、「習慣化」が大事です。
おすすめは、就寝時にきちんと時間を決めて読んであげることが大事になります!
ぜひ、思い立ったらすぐ行動に移しましょう!
▶キャンペーン中で1300円無料
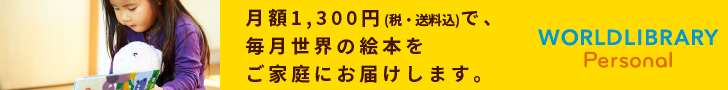
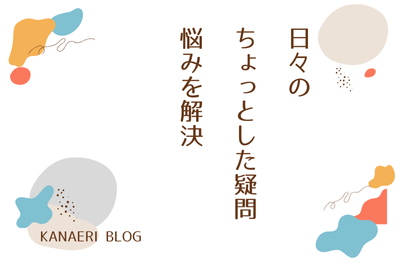
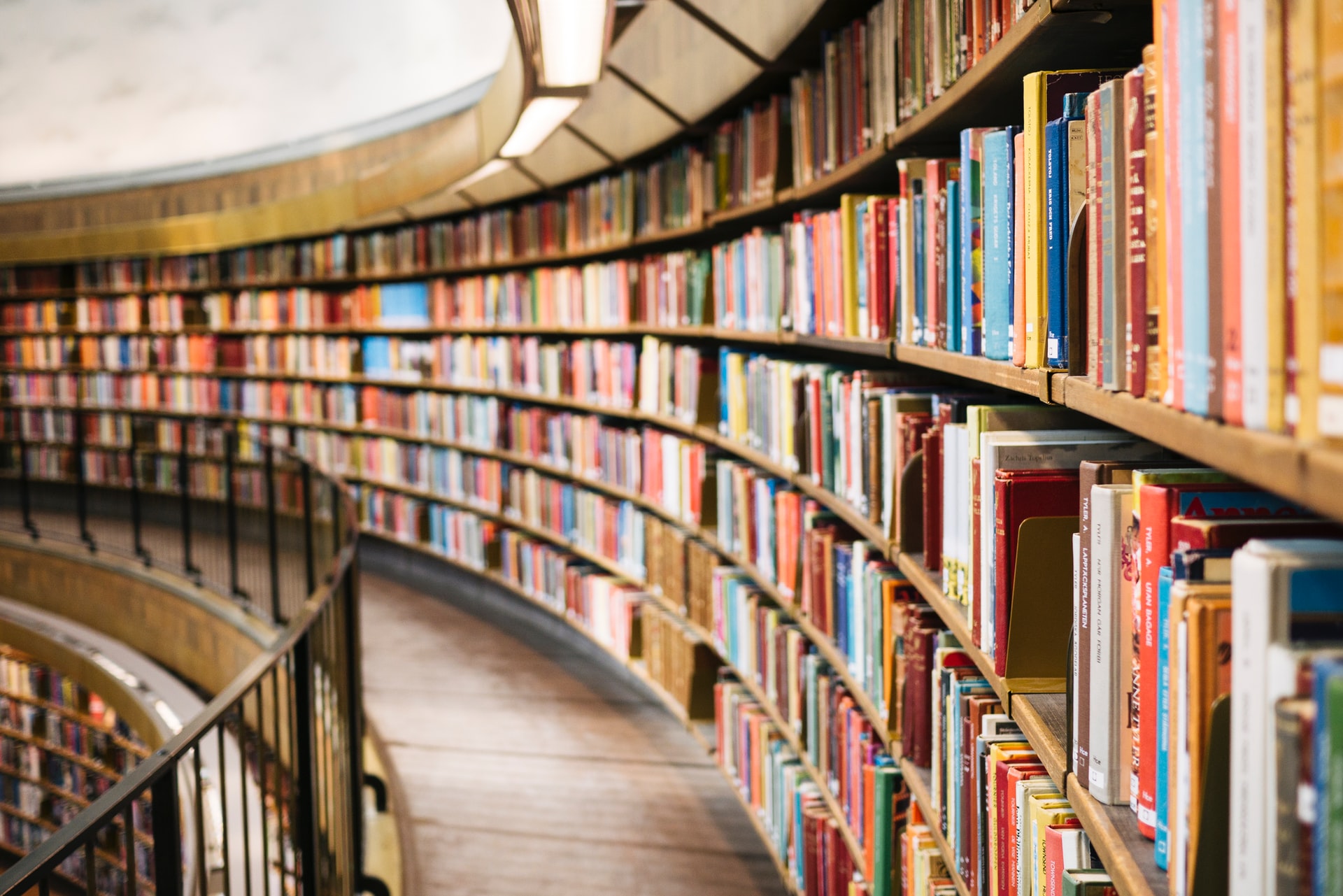



コメント